
製造現場での「チョコ停」に課題はありませんか。 ほんの数秒~数分の設備停止でも、積み重なれば生産スケジュールに影響し、納期の遅延やコスト増大につながることも少なくありません。 この記事では、チョコ停の定義や原因、そして「スマホ1台から始められる設備点検DX」が、チョコ停削減にどのように貢献するのかを解説します。
2025/07/25 公開
チョコ停とは?意味・定義・英語・正式名称・・・・・・ドカ停との違いまでわかりやすく解説!
チョコ停の定義と意味
チョコ停とは、設備が短時間にわたって停止する現象を指しますが、
具体的には数秒から数分程度の停止を指し、頻繁に発生することが特徴です。
この短時間の停止でも、積み重なれば生産効率に大きな影響を及ぼします。
チョコ停の英語・正式名称・類義語(言い換え)
チョコ停は英語では「minor stoppage」や「short stoppage」と表現されることが一般的です。
正式名称は「短時間停止」、「小停止」や「瞬間停止」といった言い換えもあります。
いずれも、短時間で頻繁に発生する停止現象を指していますね。
チョコ停とドカ停の違い|小停止と大停止の境界
「チョコ停」と「ドカ停」の違いを表にまとめてみました。
| チョコ停 | ドカ停 | |
|---|---|---|
| 意味 | 数秒〜数分程度の短時間停止 (※停止時間に明確な定義はありません。) |
数十分〜数時間以上に及ぶ長時間停止 |
| 発生頻度 | 頻繁に起きる | 稀にしか起きない |
| 原因 | 小さな設備不具合、人為ミス、材料のつまり等 | 機械の故障、ライン停止、重大なトラブル等 |
| 対応 | 現場作業員で対応可能 | メーカーや保全部門の協力が必要 |
| 影響度 | 小さいが積み重なると大きなロスになる | 一回あたりの影響が非常に大きい |
| 予防のしやすさ | 点検や運用の見直しで未然に防ぎやすい | 保全体制・予兆検知システムの導入が必要 |
チョコ停が現場の生産性に与える影響
チョコ停の蓄積は、単なる時間ロスにとどまらず、以下のような深刻な影響をもたらします。
- 生産スケジュールの乱れ → 納期遅延
- 設備の非効率稼働 → 人件費・エネルギーコストの増加
- 作業員のストレス増加 → 品質不良や労災リスクの増大
だからこそ、チョコ停の発生原因を正しく把握し、迅速に対処できる現場づくりが重要です。
次章では、チョコ停の主な発生原因をご紹介します。
なぜチョコ停は起きるのか?その主な原因

影響は小さいが、積み重なると企業の大きな損失につながる「チョコ停」。
ここでは、チョコ停の主な原因と、対策を講じるためにまず考えることをまとめました。
原因その①
【設備起因のチョコ停】
設備の不具合が原因で発生するチョコ停──。
たとえば、センサー誤検知、機械の老朽化やメンテナンス不足によって、予期せぬ停止が頻発することがあります。また、設備設計上の問題や、使用する部品・材料の品質も原因になるケースがあります。
▼POINT:まずは設備の“状態と傾向”を見える化しよう!
設備起因のチョコ停は、定期的な点検と的確な保守管理によって未然に防ぐことが可能です。
特に、過去の停止傾向を“データで可視化”し、変化を早期に察知することが重要です。
『WIZIoT(ウィジオ)』を活用すれば、スマホで現場の点検記録や状態をリアルタイムに記録・共有でき、設備の“見えない異常”にいち早く気づくことができます。
原因その②
【人為的要因によるチョコ停(操作ミス・管理不備)】
作業員の操作ミス、点検の抜け漏れ、不適切なマニュアルなども、チョコ停の原因になります。
こうした“人によるバラつき”や“属人化”が、設備の状態を見誤らせ、チョコ停を引き起こすケースは少なくありません。
▼POINT:点検作業の標準化と、記録の一元管理を!
人為ミスや管理不備を防ぐには、教育とルール整備に加えて
「だれが・いつ・どこを・どう点検したか」を一元管理する仕組みが不可欠です。
『WIZIoT(ウィジオ)』なら、スマートフォンをかざすだけで点検ができるため、
記録のばらつきがなくなり、教育効果や属人化対策としても有効。
現場の判断力を支え、管理者が的確な対応をしやすくなります。
チョコ停対策の基本と、停止時間の「見える化」方法
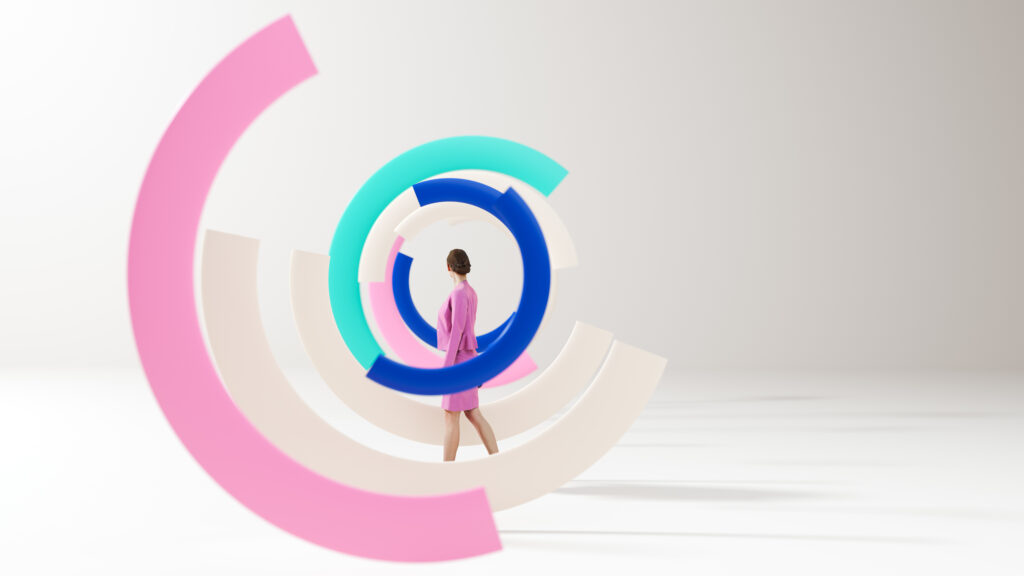
チョコ停の「見える化」はなぜ重要?
チョコ停対策を進めるうえで最も基本かつ重要なことは、「何が、いつ、どのように止まっているのか」を正確に把握することです。
チョコ停を「見える化」することで、根本原因の特定と的確な対策が可能になります。
チョコ停の時間計測とデータ収集のポイント
「見える化」の第一歩は、チョコ停の時間を正確に計測し、データとして残すことです。
以下のようなアプローチが効果的です。
・発生ごとに「いつ・どのくらい止まったか」を記録 →どの工程・時間帯でチョコ停が発生しているかを明確化 ・専用ツールやセンサーで記録の自動化・効率化 →手間を省きつつ、客観的で正確なデータ取得が可能 ・定期的なデータ分析で、傾向とパターンを把握 →再発の多い時間帯・設備・作業に対する対策立案につながる |
設備点検はアナログですか?
こうしたデータの蓄積と分析によって、現場全体での情報共有が進み、「どこに課題があるのか」が誰の目にも分かる状態になります。
まずは、「データ化」&「見える化」を進めましょう。
スマホで始める設備点検DX『WIZIoT(ウィジオ)』によるチョコ停対策の新常識!
チョコ停を減らすには、設備状況や点検の「見える化」が欠かせません。そこで注目されているのが、
スマホを活用して設備点検をデジタル化する『WIZIoT(ウィジオ)』です。
『WIZIoT(ウィジオ)』は、スマホや固定カメラを活用して、現場の点検業務をデジタル化できるツールです。
現場スタッフがスマホをメーターにかざすだけ・設備点検を記録するだけで、設備の状態や点検内容をリアルタイムに「見える化」でき、異常の兆候を早期にキャッチできます。
さらに、クラウドで情報を一元管理できるため、現場と管理者間の連携がスムーズになり、チョコ停が起きた際の「気づき」「共有」「初動対応」を迅速に行えます。
未来のトラブルを防ぐ「止まらない現場」への第一歩
今回は「チョコ停」をテーマにお届けしましたが、設備の小さな停止が積み重なることで、想像以上に生産性やコストに影響を及ぼすことが改めて見えてきました。
そしてその対策として重要なのは、「なぜ止まったのか」「いつ、どのように発生したのか」といった現場データをきちんと可視化し、傾向を読み解いていくことです。
目の前のチョコ停に場当たり的に対応するだけでは、根本的な改善にはつながりません。
日々の点検記録や異常の“兆し”を蓄積・分析できる仕組みこそが、「止まらない現場」をつくるための鍵なのだと思いました。
そうした背景のもと、近年注目されているのが設備点検業務のDXです。
点検を属人化させず、再現性のある品質管理を行うこと。
異常の一回一回に反応するのではなく、その背後にある傾向の変化を捉えて戦略的にメンテナンスすること。
そして、設備の寿命を延ばし、保全にかかるコストを最適化していくこと。
まずは、アナログ点検をデジタル化し、データとして点検結果を記録していくことから始めるのはいかがでしょうか。
『WIZIoT(ウィジオ)』は、そうした取り組みを支える設備点検DXツールです。
紙では見逃されていた兆候も、『WIZIoT(ウィジオ)』なら現場の誰もがスマホで簡単に把握できます。
点検から始まるチョコ停対策──それは現場の安定稼働を支えるだけでなく、設備の状態を見える化し、根本的な改善につなげるデータに基づく判断力を育てる取り組みです。


